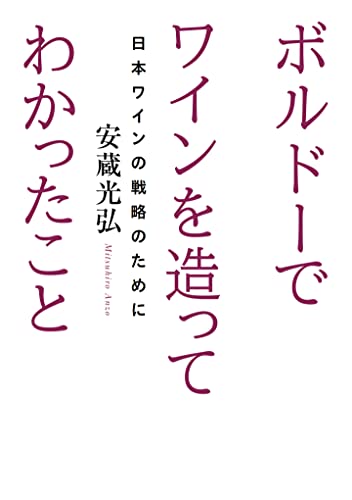とても良く出来た映画だと感心した。
かつて、実際に住んだことのある山梨のあの風景、そして実際に交流させて頂いた「日本ワイン」を取り巻く人々…。
間近に目にした“風景”と“ひと”との思い出が蘇って、映画の中がまるで目の前で現実に起こっているかの様であった。
そして、この物語は、安蔵御夫妻の物語だけでなく、事実上の主人公と言って差し支え無い故浅井昭吾先生へのオマージュを込めた物語である…。
時代は、まだ「日本ワイン」が、日本ワインと呼ばれる前の1990年代後半まで遡る…。
主人公の安蔵光弘青年が大学院を修了後、日本有数のワインメーカーであるメルシャン株式会社へと入社し、ワイン造りの“現場”に携わることを渇望して行く過程で、様々な壁を乗り越えながらも、後に伴侶となる水上(安蔵)正子さん始め、ワインへの熱い想いを内に秘める多くの仲間と切磋琢磨を繰り広げながら、やがて「日本ワインのこれから」を担う人物へと成長して行く姿を描いた群像劇である。
それより、「中の人」の私にとっては技術的な描写がとても気になっていたが、一般の方々がさほど難しさを感じることがない様になっており(そこはある程度スルーしても楽しめる。もちろん知っていると更に楽しめる・笑)、それに関しては抜かり無かったと私自身納得行くものになっている。
劇中の個々のエピソードは、流石に個人の領域まで踏み込むことから、ある程度の咀嚼(そしゃく)と脚色はあるかも知れないが、それよりも、主人公である安蔵氏と正子さん、そして彼ら2人だけで無く、日本ワインに携わる面々にとって技術的な支えのみならず精神的支柱となっている麻井宇介こと浅井昭吾先生の、そして登場する全ての人物に関する描写もきめ細やかで、抑制が効きつつも感情を込めた演技にも感心した。
これも、脇を固める俳優陣もさることながら、主人公の2人を演じた平山浩行と竹島由夏、浅井先生役の榎木孝明の秀逸な演技があってこそで、そして監督である柿崎ゆうじ氏が技術的な面だけで無く日本ワインを取り巻く背景の考証もきちんと踏まえた上で、プロットから正攻法で積み上げて行ったからに他ならない。
映画の中でもそうなのだが、実際日本のワインの歴史は、ワイン先進国である欧米に追い付き追い越せの繰り返しで、現実には気候風土などの環境面や産業としての成熟度に加え、諸制度など様々な所で課題があるのが事実で、特に銘醸地とされる有名ワイン産地を抱える欧米各国との差を埋めるところから高い壁を乗り越え無ければならない。
しかし、日本ワインを携わる面々だけで無く、世界のワイン関係者のこれまでの知見を覆い返すワイン『プロヴィダンス』が、これまで無名の産地であったニュージーランドの北島のあるマタカナの地から颯爽と現れたことに衝撃を受けただけで無く、“ワイン造りの原点”を今に蘇らせるかの様な「温故知新」な取り組みであった事にも驚かされる。
最初は半信半疑であった、浅井先生始めメルシャン社の技術陣や関係者達であったが、やがてワイン造りとぶどう造りそのものに真正面から向き合い直し、その工程を単に真似するのでは無く、彼らなりの仮説と実証を通じて、新たな挑戦に果敢に挑むのである。やがて、その成果は…、となるのである。
さて、映画のクライマックスの直前、病床の浅井先生が、『プロヴィダンス』が「亜硫酸無添加」にだけ焦点を当てられ、その言葉が独り歩きした事に対する世間の風潮を悔恨する場面が登場するが、この場面は非常に大事な所なので、私の所感を交えながら振り返って観てみたい。
それは、恐らく、これから述べる2点を、周囲がセンセーショナルな扱いの下、深く掘り下げなかったボタンの掛け違い故に、“ズレ”に繋がったと考えている。
一つは、「技術は人が自然と向き合った中で産まれた」もので、モノを創り上げる過程では取捨選択を図った上で、“手を掛けられて”行く事で磨き上げられるのを、我々人間がついつい忘れがちであることだ。
「よいもの」の定義は人によって異なるであろうが、どんな定義であれ“ほったらかし”では出来上がらない。変な話、キャンバスや紙に『無題』と称して何も描写しない絵画作品も、キャンバスや紙が無ければ存在出来ず、そうした媒体(キャンバスや紙)を作り得なければ存在出来ないのはちゃんと描写されている作品と同等で、むしろ理念において稚拙なところが無きにしもあらずな所も散見されるのでは…、と思わずにいられない。
それは、今FIFAワールドカップカタール大会の開催でホットな話題のスポーツでも同様で、高度な戦術もさることながら、基本的なキック・トラップをこなして、ボールを「誰かがゴールに向かって蹴らない限り」サッカーでは得点は産まれないのだ。ボールを置いて“ほったらかし”にすれば、勝手にボールはゴールには入らないのである。これは、相対するチームにも全くもってイコール・コンディションなのである。そして、ボールを蹴る・受けるは率直に言うと物理の中での、「モノが何で動くか?」の原理に基づいているもので、蹴られたボールが飛ぶのも「自然な動き」なのである。
昨今は、環境問題への意識の高まりなどがあるが故に、科学や技術への警鐘が盛んになり「自然回帰」が唱えられるようになっているが、そもそも科学や技術は、人々が経験知や感覚で知った自然現象を抽象化して体系的に整えたものであって根は“自然”に基づいた存在であることから、自然と対抗する存在では無いのだ。むしろ、こうして抽象化して体系的に整えたのは人間であり上手く使いこなさなければならないのは人間である。そして、何かを創り出す限り、それは、機械的な工業製品に限らず、ソフトウェアや芸術作品、料理・飲み物などヒトが関わるものなんでも、「特定の技」を捨てても「別の技」が無い限り産まれないと言う事だ。
映画の中でも、『プロヴィダンス』に刺激を受け、日本で至高のワインを産み出そうと奮闘する主人公達だが、そのために「何が出来るか」を追求して亜硫酸無添加(実際は、“それ”だけでは無い)で出てくる新たな課題に向き合い、その解決策を最先端では無く「いまある技術」に求め、やるべきことを積み重ねて行く…。本当の「温故知新」とはまさにそうである事が、『桔梗ヶ原メルロー・シグナチャー(1998)』の製造過程において、丹念に映画で描写されている。
そして、もう一つが、人が見えない事象にいかに無頓着であることである。
浅井先生が「宿命的風土論を超えての向こうにあるもの」をテーマに執筆した書籍が、今我々も時をも超えて目にする事が出来る。
『ワインづくりの思想(中公新書)』
(リンク先は中央公論新社Webサイト、紹介は下記にて。)
である。
この書籍では、銘醸地神話に彩られたワインの世界で、今まで是とされなおかつ“宿命的”とされて来た「テロワール」に代表される土地固有至上主義などの様々な神話に対しての振り返りと、その反省の上に立った「産地を造るもの」の再構築に果敢に挑んだ名著で、
「見えない世界」を見て来たかのように語ることへの危惧
について、さりげなく綴られている。
この書籍では、産地・技術・品種・テロワール・つくり手の五章に分けて「ワインづくり」の仔細を詳らかにして行くのだが、単なる「博覧強記」の枠を超え、浅井先生が現地において肌で感じた事や人と触れ合った事で見えて来たモノを、血となり肉として取りこんで行くことで、今までの前提に捉われず判断して来たことを確認の上、検証している事がハッキリと見て取れる。
つまり、見えないことを「見えないの一言」で“盲目的に”追随したり或いは文字通り“無視”することで見過ごすのでは無く、自分なりの肌感で事象を積み上げ見い出そうとする足跡が随所に散りばめられているのだ(その足跡を、確固たるものとして示している文章が、エピローグの章においてドミニク・ラフォンがデュプイの「言葉」を引用した末尾の一節に全て集約されている)。
今日日が、インターネットによる世界規模での伝播とSNSの登場と発達により、ヒトは様々な情報を手に入れ活用してはいるが、現地の事情に即したモノの“リアル”は、ヴァーチャルな技術を駆使しても血肉として取り入れることは難しい。それには、流石に断片は速攻で飛び交うことが出来ても、時間の流れと経過の中で習得出来ることまでの再現は不可能であるからだ(それが出来たら、それこそ「神の領域」である(笑))。
当時、情報技術がさほど発達していなかったのも一因ではあったとしても、著者である浅井先生の飽くなき探究心と、“ドブ板行脚”で諸所を巡って得た体感を抽象化して、知識と論理に磨きをかけたことがこの名著を金字塔たるものにしていると云えよう。
では何故に、周囲が感じ得なかった“ズレ”を何故に感じる事が出来ず、人々が誤解してしまったのか…?
この上記2点を知る上で大事なことは、現場と実践にある事の重要性である。
知識が肥大化し、人の思い込みが先走ると、他の事柄からの反駁はおろか元の事象・現場からの吸い上げも見えなくなり、結果手段が目的化したり元来の目標から外れることに繋がりかねない。また、情報化の進展で目の前に向き合わなくても知りうる事が出来る様になっても、置かれた環境と時間経過を経ての事象の動きまでは、ヴァーチャル化が進化して“メタバース”なんてものが出ていても、限りなく再現が不可能である(少なくとも、“限りなく近い状況”は再現出来るかも知れないが…)。だから、「今・そこにある」ことに向き合うことに繋がると、私は確信している。
それは、サッカーアカデミーに通おうとも、ストリートサッカーに明け暮れようとも、子供はまずボール蹴る事で初めてゴールに運ぶことを知り、物理法則を知らなくとも体感的に会得するのに相通ずるものがある。そして、体感したところからの興味を引き金に
「なんでボールが飛ぶねん⁉︎」
「じゃあ、どうやってゴールに結びつけようか?」
と技を磨くのである。
(中には、「物理法則」に興味持ってくれる子も居るかもね(笑)。)
これは、単なる「現場主義」の一言で片付けられるモノでは無く、少なくともその事柄に携わる人間が、ともすれば忘れがちな視点を持つことと、そのために向けての知識の研鑽とそのためにも手と足を使いつつ、いい意味での「頭を動かす」ことを厭わないこと、すなわち「実践と英知との間の行き来」の積み重ねに他ならないのだと感じる次第である。
映画の中で、浅井先生が実際に手を動かし目の当たりに触れる事の重要性に触れるのは言うまでも無いが、ワイン造りそのものと云った華々しいところだけで無く、その周囲を取り巻く背景・事象を見て欲しい旨のことや、背景・事象から拾い出したモノから見えて来る考えを文章化して行く事の重要性を、下働きに明け暮れたり或いは現場を離れ焦燥感に苛まされる主人公に対してさりげなく諭すだけで無く、そっと後押しする中で、時には語り部として・時には好々爺の様に・そして師として最後に後事を託すかの様に言葉を絞り出す姿を通じて、浅井先生が問い掛けたかった・訴えたかったものは何か…⁉︎を、主人公の2人を通じて少しでも感じ取る事が出来ればと思う。
それが、安蔵御夫妻が映画というフォーマットで、出来る限り多くの方々に届けたかったものなのかもしれない。
日本のぶどう・ワイン造りそのものに関わる人だけでなく、「お酒」の仕事に携わる方々、そして多くの人々に観て頂きたい。
そのためにも、東京・大阪など主要都市での映画公開の千秋楽*1を迎えた今、DVD/Blu-ray等のソフト化を是非ともお願い申し上げたい次第である。
※写真は、『シグナチャー』公式サイト
https://signature-wine.jp/
より引用。
【書籍紹介】
最後に、この映画を通じて、そして日本ワインを語る上で、改めて故浅井昭吾先生が問い掛けたかったもの・訴えたかったものに直に触れることが出来る著作が、今でも目にすることが出来る。
時をも超えて響く『言葉』から、感じ取って頂ければと思う。
1)『ワインづくりの思想(中公新書)』(Kindle版あり)
浅井先生の著作で、今すぐに手に取ることが出来、是非とも読んで頂きたい一冊。内容は、上記寸評にも記してある通りだが、現代にも通じる名著。Kindle版でも入手可能なので、まずはこれから!
2)『5本のワインの物語』
安蔵御夫妻の足跡を記した自叙伝形式での物語で、映画のストーリーのいわば下敷きにもなっている(第1章と2章がほぼ該当する)。
書籍では、御夫妻の現在についてまで描かれ、ご本人でなければ書けなかった所まで著述されているが、感傷に流されることなく事実を丹念に綴っておられる。映画をより深く知るための一冊でもあるが、これ単体でも是非手に取って頂ければと願う。
3)『麻井宇介・著作選』
先述の『ワインづくりの思想』以外にも、浅井先生は多数の著作を残し、その哲学を余すところなく記されているが、現状で入手可能なのはこちら。本当は、日本の酒類行政についてまで赤裸々に記された激動の戦後酒史『酒・戦後・青春』もセレクションの中にあればベストだったのだが…。
4)『ボルドーでワインを造ってわかったこと〜日本ワインの戦略のために』
安蔵氏が、武者修行のためにフランス・ボルドーへ渡った時の体験を基に記した現地のありのままの姿。決して名醸地が「約束の地」ではなく、歴史の積み重ねとそこで真摯に携わる人々が存在したからこそ成立していると痛感させられる。日本というワイン産地に足りないものは何かを問い掛け、未来に向けての提言がこの本の中にあると言ってよい。
*1:現在、地方都市で順次公開中。そして、東京方面では別の映画館での公開が決定したとのこと。詳しくは映画の公式Twitterアカウントにて。